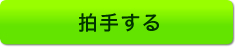メニュー
筆さんぽ
桜餅一つ、100万円
2024年03月11日 
テーマ:エッセイ
かつての仕事仲間から、飲み会に誘われた。ぼくはいま、ワケあって禁酒禁煙しているので断ったが、「まあ顔ぐらい見せろよ」といわれ、人さまにご披露するような顔ではないが、しぶしぶ腰を上げ、宴会の仲間になるが、これが間がもてず合コン初体験の女子のようにもじもじしていると「まあ、一杯ぐらいいだろう」とお銚子を目の前にぶら下げられる、年を重ねると妙に意固地になって「ならぬものはならぬ」と会津の藩士のようなことを言って、あとですこし悔やむ。
そんなものだから、飲み会はあきらめた。その仕事仲間の一人から「本の交換会」に誘われた。「喫茶店でやるから」と付け加えるものだから、いそいそと出かけた。ぼくはかつて、筑摩の宮沢賢治全集や岩波の夏目漱石全集などを本棚に並べて満足していたが、あるとき、「本は読むもので飾るものではない」と?オイやメイたちに、好きなのをもっていけと、全部処分した。
いまは、かつての仕事仲間などが集って、自分の好きな本を持ち込む「読書会」や本の交換などを楽しんでいる。
さて、タイトルの桜餅。
「はい、一つ100万円です」
といえば、ばかばかしくて誰も買わない。
これは、秀吉の「醍醐の花見」のゆかりの桜餅だよ。
「これはすばらし和菓子だ」と桜餅を一個一億円で売りにゆく人はいない。
絵画なら、人にわかりにくい。
かつて絵画ブームのころ、国立西洋美術館の常設展の部屋で、ピサロの「立ち話」をみていた。
そのとき、どこかで読んだ、こんな話を思い出した。
「この絵、光の香りまでも感じるでしょう。
ペルーのピサロ一代の傑作です。
三億円ならお買い得ですよ、来年には十億円になります」
ペルーのピサロとは、いうまでもなく16世紀のスペインの大悪漢で、南米へ黄金を取りに行き、インディオをさんざん殺した。
もっとも、19世紀の印象派の画家にもピサロがいるが、こちらはフランス人である。
ところが、「絵画ブーム」におどった商人たちは素人同士だから、ピサロが何であれ、おたがい頓着ない。
「鑑定書」もあります。
どこかの素人が書いたものであろう。素人が素人に売るのだから、素人の鑑定書があってもいい。
ぼくは絵が好きだが
ときにほしいとおもうこともあるが
買おうとは思わない。いや、高くて買えない。
本にしても
たとえば「初版本」などには興味はなく
本は、まとまると、断捨離よろしく「資源ごみ」として処分する。
「これは高く売れますよ」と
知人の好事家(こうずか)に叱られたこともある。
好事家とは、辞書によると
「物好きな人。また、風流を好む人」とある。
好事家同士の仲間うちは
「マイ・ガーデン」であろうか。
たがいに見せ合って、たのしむ。
「漱石の『坊っちゃん』の春陽堂版の初版本ですね。おしいことに、表紙に大きなシミがありますな」
そんな無垢な人が数百人いればいいほうである。
その数百人のあいだで、めずらし本がたらいまわしされて、かぼそく相場が成りたっていた。
冒頭でふれた「自分の好きな本を持ち込む読書会や本の交換会などを楽しんでいる」のも、その類といってよく、いわゆる「マイ・ガーデン」である。
ところが、その「マイ・ガーデン」に
儲けや「資産」だけを考える
商人が踏み込んでくると
「マイ・ガーデン」はたちまち枯れる。
絵画鑑賞も、好事家だけのひよわい世界であった。
絵画は桜餅のようにだれでもわかるというものではない。
また、わからなくても、決して恥ずかしいことではない。
「キミは、この絵のよさがわからんのかね」
といわれて、知能の欠陥を指摘されたように思ったことがある。
これは学校教育の欠陥ではないだろうか。
絵は、「うまさ」ではないであろう。
人間の中には「美」というものに
過敏な、もって生まれた才能をもつ人がいて
「ただならぬ思い入れ」というイースト菌を加えて
膨れ上がらせたのが「名画」になるのであろう。
展示されてみると、描き手の執念が消えて、みる側には快楽になる。
それを、それぞれの形であっても、快楽と感じるのは、気質としてはすでに好事家であろう。
好事家の感情は、ダイヤモンドの原石の虜になった人に似ていないだろうか。
原石の無色透明の気高さを感ずるのである。
ときに、もっとも美しく輝く形にカットして「宝石」にすることは、ゆるされる。
しかし、土足で踏み込んで、原石どうかかわからいものをカットして売りさばくのは、たんなる商売人である。
まして、なにほどでもない
コメントをするにはログインが必要です