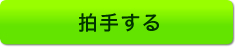メニュー
最新の記事
-

【New!】 6月の綺麗な風 -

緑の道を歩く -

麺類が好き -

夫のあなたは誰なの? -

新緑がまぶしい
テーマ
- エッセイ ( 36 )
- ショートストーリー ( 1 )
- 俳句鑑賞 ( 7 )
- 映画 ( 3 )
- 本 ( 1 )
- 短歌 ( 1 )
- 筆さんぽ ( 45 )
- 読書案内 ( 15 )
- 読書案内 ( 0 )
- 連載エッセイ ( 5 )
- 連載物語 ( 2 )
- 連載物語 ( 2 )
- テーマ無し ( 8 )
カレンダー
月別
筆さんぽ
新緑がまぶしい
2024年05月24日 
テーマ:筆さんぽ
どんよりと雲が低い日がつづくと気も滅入り、キーボードを叩くのも億劫になって、ブログともしばらくご無沙汰していた。
天気の良い日に、憂さ晴らしに街にでた。
新緑の初夏は、一年のうちでもっとも生き生きとして美しい季節のように思う。山や渓谷の自然林はもちろんだろうが、コンクリート砂漠のような都会の街路樹も目がさめるような新緑に萌え出るころは、人間も生き生きとしてくる。
銀杏並木の巨木は日本の都市の代表的な街路樹の一つだが、新緑の萌え出るころは、まるで緑のイルミネーションがともったように鮮やかである。プラタナス(鈴懸)が初めて街路樹になったのは明治のころで、東京の田村町(西新橋)だという。
これによく似て品位があるのは、ユリノキだろうか。東京・赤坂迎賓館周辺のものが立派だという。あのあたりに仕事場をもったことがあるが、うかつにも見逃していた。
上野の国立博物館前と、新宿御苑にあるユリノキは何十メートルもある巨木で、これは実際に見たことがあるが、これもうかつなことに、花が咲くことを、草花に精通している知人の写真で知った。高く茂った葉の間に咲いていて目立たないので、これからは注意してみようと思う。
知人の話では、ぼくは見ていないが、マロニエと親類筋の橡(トチノキ)の並木が東京・警視庁前の桜田通りで初夏には美しい白や薄紅の花を咲かせるという。
東京の銀座は、古い映像などをみると、柳並木が名物だったそうだが、いまはない。首都の顔としてはいかがなものか。
街路樹には公害に強い木というのが常識のようだが、むしろ公害に弱い木を植えるべきだという意見もある。
時ならぬ落葉がハラハラと散れば、それは公害を知らせる警報で、放置すれば、つぎは人間の番ですよと警告してくれるからだという。一理あるが、ここは科学の測定を待ったほうがよいだろうと思う。
日本の自然林の新緑は世界に類がないないほど美しいといわれる。それは広葉樹の種類が多く、新緑の色彩、濃淡が複雑微妙だからであろう。
街路樹は、平安京に柳と槐(エンジュ)が約17メートル間隔に植えられなど、1200年以上前から整えてきたと、何かで知った。
日本人は街路樹に、その機能だけではなく、自然美を求めてきたのであろう。
新緑やかつて我はうつくしき 蜂鳥
コメントをするにはログインが必要です