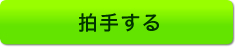メニュー
筆さんぽ
はじめての異国体験はプラハだった
2024年02月10日 
テーマ:エッセイ
プラハは石甃(いしだたみ)の街である。
プラハで見た石甃のタタミという文字は、カタカナや平仮名ではしっくりとこないし、かといって畳みという漢字だとなおさら合わない。
甃という漢字は、たとえば井戸などの内側に貼り整える瓦の意である。なるほど、隙間なく一面に貼り込んである様子がいい。苔がよく似合うし、歴史も感じられる。街中に散らばっている石甃の色と形は、その舗道が作られた年代によってそれぞれ異なる。
プラハを訪れたころはこれが気になって、街を散策するときは下ばかりを見て歩いていた。
宗教改革のヤン・フスの像がある旧市街広場の石甃は銀灰色。銀といっても金属的な光沢はなく、灰色の明るい部分が銀色のような感じを受ける、といった程度のものである。
カレル橋の上の石甃は砂目が少し暗い紅花色。これにくらべてプラハのメインストリート、バーツラフ広場の石甃は藍鼠色。美しい石甃はプラハ城周辺でよく見かける。
観光客が少ない裏道は、柑子色ほど鮮やかではないが、ワインのコルクのような明るい黄茶色である。ひとつの石の形はほぼ正方形でそろえてあるが、よく見ると、角がとれて丸味のある石、三角形にちかい石、ペンタゴンの石などさまざまだが、舗道全体としてみると、これは気にならず、ステンドグラスのようなバランスのとれた幾何学模様をつくっているから不思議である。この不思議さはプラハの街の気分に似ている。
若いころの話になるが、ぼくの初めての異国体験は、ニューヨークやパリ、ロンドンではなく、東ヨーロッパのチェコスロバキア(現チェコ共和国)の首都、初夏のプラハであった。
(事情は長くなるので省かせていただくが)
思いがけない好運を得て、つまり「棚から牡丹餅(中島みゆきさんは「棚から本マグロ」といっていた)」」で、プラハに「派遣」されることになった。
プラハを散策すると、気になるのは石甃だけではなく、石の建物である。何しろ、二百年、数百年という石の建物に囲まれていると、「木の文化」のなかで育ってきた人間にとっては「重圧感」すら感じるのである。
喉が渇いた。
「黄金の虎」という名の店で、通訳のSさんとピーヴォ(ビール)を飲んだ。午後四時ころだというのに、十坪ほどの店内は混んでいて、菜っ葉服の工場労働者が目立った。カップルがビールを飲んでいるテーブルが空いていたので、会釈して通訳のSさんと一緒に座らせてもらった。(学生時代からお気に入りだった)缶ピースをテーブルに置いてビールを飲んでいたら、カップルの男性のほうが、缶ピースをジロジロ見ているので、すすめてみた。(通訳のSさんを交えて話す)。
男は電気工事技師、金髪の童顔で、同じ金髪の口髭のたくわえ、無口な青年であった。なかなかいける煙草だという顔をしながら、連れの女性にも進める。女性は若いころの"カトリーヌ・ドヌーブさんみたいに、抜けるような白い肌をもつ、キリッと締まった金髪美人で、こちらは顔に似合わず、下町のオバちゃんのようによくしゃべる。
似合いのカップルだね、という挨拶に対してそうではないという。長々としゃべっていたが、二人とも「バツ1」で、近々結婚するという。
チェコスロバキアで起きた自由を求めた「プラハの春」は、この旅のかなり前に起きたことだが、この再婚は「プラハの春」ではないかと思った。
店を出て、旧市街広場の野外のカフェで、コーヒーを飲みながら酔をさませていた。通訳のSさんは、ぼくよりもできあがっていて、よくしゃべった。
「私の奥さんは日本人です」
「えっ、それはいい」
といって笑った返事は
「離婚しました」であった。
どうしてと聞こうとしたがやめて、
目線をそらし
広場の中央にある宗教改革のヤン・フスの像をみていた。
フスの口癖は「真実」であった。
人は、それぞれの心の正義を模索し、より神に近い生活を送るべきだというのである。中世末期の欧州では、「個人」という概念がようやく脚光をあびてきたころである。
王や教会の言いなりになるのではなく、個人の信念に基づいて生きること。これが、フスの言う「真実」であった。
と思ってSさんをみると
気持ちよさそうに「船を漕いでいた」
これも「プラハの春」である。
コメントをするにはログインが必要です