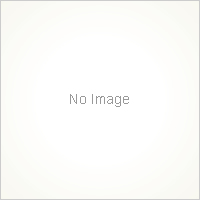メニュー
最新の記事
テーマ
カレンダー
月別
- 2017年06 月( 2 )
- 2017年01 月( 8 )
- 2016年07 月( 2 )
- 2015年10 月( 2 )
- 2015年09 月( 2 )
- 2015年05 月( 4 )
- 2015年04 月( 2 )
- 2015年02 月( 8 )
- 2015年01 月( 4 )
- 2014年12 月( 5 )
- 2014年04 月( 2 )
- 2014年02 月( 3 )
- 2013年07 月( 1 )
- 2013年06 月( 1 )
- 2013年03 月( 2 )
- 2013年02 月( 8 )
- 2013年01 月( 7 )
- 2012年07 月( 1 )
- 2012年03 月( 1 )
- 2012年02 月( 2 )
- 2011年11 月( 1 )
- 2011年10 月( 1 )
- 2011年09 月( 1 )
- 2011年07 月( 2 )
- 2011年06 月( 4 )
- 2011年05 月( 7 )
- 2011年01 月( 1 )
- 2010年12 月( 2 )
温泉大好き人間
サイクリング 瀬戸神社(金沢八景)
2013年01月28日 
テーマ:テーマ無し
1月27日(日)は朝からの好天気、まさに小春日和。風がないので自転車に乗って逗子・小坪漁港までゆっくり漕ぎ出した。途中、金沢八景に近くの「瀬戸神社」に寄ってみた。去年の秋から暮れにかけ拝殿や本殿の屋根の銅板を葺き替え、屋代そのものも補修し白木が真新しい。さらに鈴から下がる太い綱も新しくカラフル(地味な色だが)になっている。ところでボクはその鈴を一度も鳴らした事が無い。神社に行くと大げさにガランガランと鳴らして拝する人がいるが、神様に合図するのと自分の邪気を払う為らしい。当初、早朝散歩が多かったので、ボクは神様を起こしてはいけないと思い、そおっと賽銭をすべり込ませる様に入れ、手を合わせるだけにしている。その拝み方をずうっと続けている。瀬戸神社正面、国道16号から奥行が少ない瀬戸神社、屋根の銅板が新しい瀬戸神社の由緒より抜粋=大昔、三浦半島の入口、金沢八景の泥亀町から釜利谷東一帯は大きな入江でした。この入江と平潟湾とは、今日の瀬戸橋の位置にあたる狭い水路状の海峡でつながっていました。そしてこの小さな海峡は、潮の干満の度に内海の海水が渦を巻いて出入りする「せと」でした。古代の人は水流の険しい「せと」を罪穢れを流し去ってしまう神聖なところであるとして、豊な幸をもたらしてくれる神々をここに祭りました。 これが瀬戸神社の起源です。神社の隣接地からはすでに古墳時代には祭りが行われていたことを証する祭祀遺物が出土しています。 鎌倉時代、幕府を開いた源頼朝は、治承4年(1180年)伊豆での挙兵にあたって御利益を蒙った伊豆三島明神(三島大社)の分霊をこの「せと」の聖地に祭り、篤く信仰しました。社殿の造営もおこなわれ、今日のような神社の景観ができ上がったのは概ねこの頃のことです。 以後、金沢(六浦)の地は港町として発展し、鎌倉と関東一円を東京湾や利根川を水系利用して結ぶ水上物流の集散地となりましたから、執権北条氏、ことに金沢に居を構えた金沢北条氏、また足利氏や小田原北条氏の崇敬も篤いものがありました。ことに江戸時代には徳川家康は社領百石を寄進しています。そして武家のみならず、名勝金沢八景の中心の神社として江戸の町民にまで広く崇敬者はひろがり、文人墨客も多く当社を訪れました。=以上抜粋今年になって住まい近くのお寺・神社を三箇所、このブログで紹会しました。称名寺(金沢文庫)、富岡八幡宮(富岡)、瀬戸神社(金沢八景)。歴史のある古刹が歩いて..
>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)
この記事はナビトモではコメントを受け付けておりません