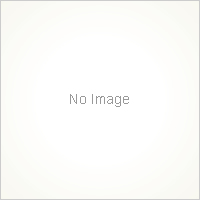メニュー
最新の記事
-

メキシコ便利帳が発刊されました! -

長らくご愛顧いただきありがとうございました。 -

メキシコ生活情報の更新 〜ラジオタクシーをアプリで呼ぼう〜 -

2015年秋の愛妻弁当まとめ -

10月の八ヶ岳(3) 〜コゲラとツリガネニンジン〜
テーマ
カレンダー
月別
- 2016年12 月( 1 )
- 2015年11 月( 3 )
- 2015年10 月( 4 )
- 2015年09 月( 10 )
- 2015年08 月( 4 )
- 2015年07 月( 8 )
- 2015年06 月( 5 )
- 2015年05 月( 7 )
- 2015年04 月( 6 )
- 2015年03 月( 9 )
- 2015年02 月( 9 )
- 2015年01 月( 8 )
- 2014年12 月( 7 )
- 2014年11 月( 6 )
- 2014年10 月( 12 )
- 2014年09 月( 4 )
- 2014年08 月( 17 )
- 2014年07 月( 8 )
- 2014年06 月( 21 )
- 2014年05 月( 9 )
- 2014年04 月( 20 )
ジェット妻ストリーム2
お盆のしたくとお盆玉
2014年08月13日 
テーマ:テーマ無し
長男の夫のところに、長女のわたしが嫁ぎました。実家は姉妹しかいませんので、親のお仏壇をわたしが受け継ぎ、お盆前に小さな現代仏壇というのに買い替えて、マンションの寝室のベッドのそばに置いています。
いつかは夫の実家のお仏壇もやってきます。
わたしは墓守り娘として、子どもの時から、本家(父も長男)の盆暮れの営みを父から教えられて、親戚の集まりや、お墓やお寺さんの付き合いにも父について出かけていました。
亡き父の兄弟が存命の間はお仏壇をおいて、先祖代々のお墓を守る墓守り娘です。私が死んだら永代供養だろうなぁと思いながら…。
老親がなくなってから、初めてひとりでお盆のお支度をしました。
精霊馬をこしらえて、お仏壇を掃除して、精霊棚をしつらえます。
きゅうりのお馬にのって早くおいでください。茄子の牛にのって牛歩でゆっくりお帰りなさい。
ちいさく心の中でいいながら…。
マンションタイプの小さなお仏壇なので、ほうづきや、里芋の葉っぱ、みそはぎは省略。
盆ござをひいて、父や母の好きだった物を供えて、お花を買って供えました。
よく考えてみれば、お盆は、ご先祖様をお家にお迎えする日。
亡くなった両親は、都会のマンションに暮らすわたしの家にちゃんと戻れるのでしょうか?
本来なら、お墓に出向いて小さな蝋燭に火を灯して提灯にいれてご先祖さまをお家までお連れするところ。
子どもの時は、早々に浴衣になって、ピンクの提灯を得意げに提げてお墓へ行ったのでした。
お迎え火の麻幹(おがら)をマンションのベランダでこっそり燃やしてみましたが、立ち上る煙がちょっと多すぎて、あわてて2本だけ。これじゃ空から見つけられないかもしれませんね。
お墓参りはしても、こういうお盆の各地方、各家庭での風習は、もう都会ではなくなってしまいました。
夫の実家は、地方の出身にもかかわらず、東京のお仏壇に精霊棚を作ったりはしません。
メキシコの死者の日は、まさにこのお盆と同じ風習で、それはにぎやかに国中がこの日のしつらえをしていたけれど、日本は花屋さんの片隅に、ひっそりと盆ござとほうづき、里芋の葉っぱが売られているだけ。
近頃は、お盆玉というのがあるんですって。帰省した孫にお年玉のように、「お盆玉」
後継者がいなくなりつつあるお墓やお仏壇。しっかりお墓の掃除をして、供養ができたらもらえるっていうのが大事かなと思いますが。
父と母は、ようやく帰国した嫁いだ娘のマンションにやってきたのでしょうか?
ちょっと感傷的になって、わたしも年をとったのだなと思います。
周りには、今年がご両親の新盆という方もいらっしゃっても、お迎えのお提灯はもう買わないみたいだし。
クリスマスツリーは飾れても、精霊棚なんか知らない我が子たち。
たぶん、もうこういうことは我が子にも継承されてはいかないのでしょうと思うと、日本の風習や伝統文化がどんどん消えちゃうとおもうと寂しいわ。
合理的に、今時そんなこと!って言われても、やっぱりこういうことは割りきれませんからね。
毎度ご訪問ありがとうございます。
こんなランキングに参加しています。お時間があれば、ぽちっとお願いね!
にほんブログ村
にほんブログ村
>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)
この記事はナビトモではコメントを受け付けておりません