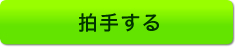メニュー
最新の記事
-

【New!】 『コード・ガールズ』 <旧>読書日記1603 -

【New!】 『実は、拙者は。』 読書日記395 -

『鈍足バンザイ <旧>読書日記1602 -

『のっけから失礼します』 読書日記384 -

『100万回死んだねこ』 <旧>読書日記1601
テーマ
カレンダー
月別
- 2024年06 月( 13 )
- 2024年05 月( 26 )
- 2024年04 月( 26 )
- 2024年03 月( 26 )
- 2024年02 月( 24 )
- 2024年01 月( 27 )
- 2023年12 月( 31 )
- 2023年11 月( 30 )
- 2023年10 月( 31 )
- 2023年09 月( 30 )
- 2023年08 月( 31 )
- 2023年07 月( 27 )
- 2023年06 月( 30 )
- 2023年05 月( 31 )
- 2023年04 月( 28 )
- 2023年03 月( 31 )
- 2023年02 月( 26 )
- 2023年01 月( 31 )
- 2022年12 月( 31 )
- 2022年11 月( 29 )
- 2022年10 月( 15 )
- 2022年09 月( 15 )
- 2022年08 月( 15 )
- 2022年07 月( 17 )
- 2022年06 月( 15 )
- 2022年05 月( 15 )
- 2022年04 月( 15 )
読書日記
『下流老人と幸福老人』 読書日記376
2024年05月25日 
テーマ:読書日記
三浦展『下流老人と幸福老人』光文社新書(図書館)
この本も図書館の返却ワゴン(返却された本を棚に戻すためのワゴンで開架棚の本と同じように閲覧・借り出せる)に積まれているものを見て借りだしたもの。図書館の開架棚は少しずつゆっくりと入れ替わっているものの、パッと見にはあまり変わり映えしないけれども、このワゴンの本は絶えず入れ替わっているので良く覗いてみる。
さて、著者は『下流社会』(光文社新書)で有名であるが、「市場調査を土台とするしっかりしたデータにもとづいて、分析する」のが特徴とも言える手法を用いる。だが、その手法と著書については肯定的評価と否定的評価が入り交じっている。
この本は2016年3月刊であるが、amazonでは次の様に紹介されている。
【内容紹介】
『下流社会』刊行から11年。そこでの予言はほぼ現実のものとなった。学生、非正規雇用、シングルマザー、そして高齢者などを中心に日本人の経済生活の下流化が進みつつある。本書は、こうした下流社会的状況の中から65歳以上の高齢者(シニア)の下流化の状況を分析するとともに、お金はないが幸福な老人になる条件は何かを考える。
結論から言えば、たしかに金融資産が多いほうが幸福度は高い。だが、資産が多くても幸せではない人はいるし、資産が少なくても幸せだという人も半数ほどいる。世の中、お金がすべてではない。お金がそんなになくても幸せな「幸福老人」を増やすことが、これからの超高齢社会の設計のために重要である。
【目次】
はじめに 下流社会の中に「幸福老人」を探す
第1章 上流老人と下流老人
第2章 上流老人はさびしく、下流老人は買いたいものが買えない
第3章 何が人生の失敗か。どういう人が幸福か
第4章 資産がなくても幸福な人 資産があっても不幸な人
第5章 多世代共生、多機能、参加型社会が幸福老人を増やす
阿佐谷おたがいさま食堂/okatteにしおぎ/タガヤセ大蔵/ゴジカラ村 ぼちぼち長屋/シェア金沢
巻末インタビュー 藤野英人
あとがきにかえて
上の内容紹介で、「結論から言えば」以下では誰でもが漠然と判っていることが書いてあり、それでどうするが本文にあるかと思って読んだが、章になっていない末尾に少しだけあり、全体に何も書いていないに等しかった。
本の体裁としては、調査した質問項目ごと(と思われる)に棒グラフ化をしていて左ページにそのグラフ、右ページにその概略内容が書いてある。全216ページの内第4章までの144ページまでがこの形式であり、残りのうち50ページほどが「幸福(だと思われる)老人を生み出している施設や施策の紹介」である。
要するに本書は調査の結果報告を一般の目に触れやすい「新書」という形で発表した様なものであった。かつ、そこで示される概略は各章の題名となっていて、ある意味予想された通りのことである。目新しい知見があったのだろうか?と思えるものであり、極端な話をすれば、データをまとめたものであるはずが、求める結論を得る為のデータ収拾では無かったかとすら思われる。実態をデータで示すことは重要ではあるけれど、ではこのデータを元にどうするか、どうしようかというものが見えて来ない様に思えた。←上流か下流か、幸福かどうか、という2つの指標から老人世代を4区分した時に「下流かつ不幸な老人(調査対象全体の約5%)」をどうするか、どうしたら良いのかが見えて来ない。
最後にこの本の基礎となったデータは以下の通り(本書p18に記載)
★「シニア調査」
・調査主体:株式会社三菱総合研究所
・調査地域:全国47都道府県
・調査対象:50歳以上80代までの男女(本書では65歳以上を集計)
・有効サンプル数:6314人
・調査方法:WEB調査
・調査時期:2015年6月
★「シニア追加調査」
・調査主体:株式会社株式会社カルチャースタディーズ研究所、三菱総合研究所
・調査地域:全国47都道府県
・調査対象:「シニア調査」の回答者を対象に追加質問として実施
・有効サンプル数:65歳以上500サンプルを回収
・調査方法:WEB調査
・調査時期:2015年11月6日〜9日
※WEB調査ということによる偏りはないのだろうか。貧しい老人が調査対象から漏れているのでは無いだろうか。
(2024年4月29日読了)
コメントをするにはログインが必要です