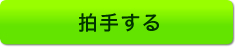メニュー
最新の記事
-

【New!】 『三千円の使いかた』 <旧>読書日記1598 -

【New!】 『インド旅行記 1 北インド編』 読書日記379 -

『仏像ぐるりのひとびと』 <旧>読書日記1597 -

『いちばん初めにあった海』 読書日記378 -

『お寺さん崩壊』 <旧>読書日記1596
テーマ
カレンダー
月別
- 2024年06 月( 2 )
- 2024年05 月( 26 )
- 2024年04 月( 26 )
- 2024年03 月( 26 )
- 2024年02 月( 24 )
- 2024年01 月( 27 )
- 2023年12 月( 31 )
- 2023年11 月( 30 )
- 2023年10 月( 31 )
- 2023年09 月( 30 )
- 2023年08 月( 31 )
- 2023年07 月( 27 )
- 2023年06 月( 30 )
- 2023年05 月( 31 )
- 2023年04 月( 28 )
- 2023年03 月( 31 )
- 2023年02 月( 26 )
- 2023年01 月( 31 )
- 2022年12 月( 31 )
- 2022年11 月( 29 )
- 2022年10 月( 15 )
- 2022年09 月( 15 )
- 2022年08 月( 15 )
- 2022年07 月( 17 )
- 2022年06 月( 15 )
- 2022年05 月( 15 )
- 2022年04 月( 15 )
読書日記
『弟子・藤井聡太の学び方』 <旧>読書日記1593
2024年05月20日 
テーマ:<旧>読書日記
杉本昌隆『弟子・藤井聡太の学び方』PHP文庫(図書館)
本書は2018年に出版されたものが19年4月に文庫化されたもの。出版当時と今では棋士・藤井聡太の棋界での位置づけは大きく変わっている。当時はまだタイトルは取っていなかったのが今や王位・叡王・棋聖の三冠(*)であり、竜王戦でもあと1勝(2021/10/31現在3勝0敗)とタイトルに近づいている。
そんな立場の違いがあるものの本書は「はじめに」で著者が書いているように
師匠から見た弟子・藤井聡太の「学び方」をつづったものです。(中略)「学び方」とは具体的な将棋の指し手や先方を指しているのではありません。(中略)ここではもっと広い意味としてとらえています。
将棋を強くなるために要するこれらは、私たちが人生をより豊かにいきていくうえで必要な学びとも言えるでしょう。
と、読み方によっては将棋に限らず「考える必要がある」人間全般に通じる「学び方」を論じていた。
その要点は「(どのように学ぶか、ということも含めて)自分で考える」言い方を変えると「得意な学び方を見つける」ということであり、基本的な態度として「目先の得を追わない」。学ぶ側には信念が必要であり、そして、師匠としては「柔軟性」が必要だと断ずる。自分の考え方の型にはめようとしないと言うことである。
私は今までに多くの「将棋界」についての本を読んで来たが、こうした態度はどの師匠にも共通していると感じる。強くなるには結局「自分で学ぶ」しかないのである。将棋はほとんど引き分けの無い競技であり、ほぼ、勝つか負けるかのどちらかしか無い。そして、「勝つ」ことによって地位も名誉も金も得られるのがプロの世界である。
しかし、プロ棋士として大成し時代の頂点を極めていく為には、目先の勝敗にはこだわらず真理に向かって努力しなければならないように思えるし、谷川浩司9段(17世名人の襲位は引退後)は棋士には「勝負師」「研究者」「芸術家」の3つの側面を持つべきだという持論を持っている。言い換えると「勝負師」であるだけでは一流になれないのである。中原誠16世名人(師匠は高柳敏夫名誉九段)も羽生善治19世名人(襲位は引退後。師匠は二上達也九段)もみなそうであった様に思えるし、藤井聡太三冠もその系譜に連なるのであろう。
(2021年11月1日読了)
(*):これをアップしている今は藤井八冠であり、全タイトルを独占している。
コメントをするにはログインが必要です