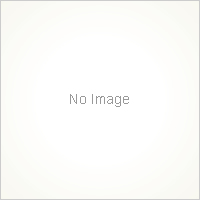メニュー
最新の記事
テーマ
カレンダー
月別
- 2024年06 月( 7 )
- 2024年05 月( 9 )
- 2024年04 月( 9 )
- 2024年03 月( 9 )
- 2024年02 月( 11 )
- 2024年01 月( 10 )
- 2023年12 月( 11 )
- 2023年11 月( 8 )
- 2023年10 月( 11 )
- 2023年09 月( 10 )
- 2023年08 月( 9 )
- 2023年07 月( 8 )
- 2023年06 月( 9 )
- 2023年05 月( 10 )
- 2023年04 月( 13 )
- 2023年03 月( 14 )
- 2023年02 月( 10 )
- 2023年01 月( 12 )
- 2022年12 月( 11 )
- 2022年11 月( 10 )
- 2022年10 月( 8 )
- 2022年09 月( 12 )
- 2022年08 月( 10 )
- 2022年07 月( 11 )
- 2022年06 月( 10 )
- 2022年05 月( 11 )
- 2022年04 月( 11 )
- 2022年03 月( 13 )
- 2022年02 月( 9 )
- 2022年01 月( 10 )
- 2021年12 月( 13 )
- 2021年11 月( 11 )
- 2021年10 月( 13 )
- 2021年09 月( 12 )
- 2021年08 月( 8 )
- 2021年07 月( 10 )
- 2021年06 月( 12 )
- 2021年05 月( 15 )
- 2021年04 月( 14 )
- 2021年03 月( 10 )
- 2021年02 月( 11 )
- 2021年01 月( 12 )
- 2020年12 月( 15 )
- 2020年11 月( 15 )
- 2020年10 月( 13 )
- 2020年09 月( 13 )
- 2020年08 月( 13 )
- 2020年07 月( 13 )
- 2020年06 月( 12 )
- 2020年05 月( 15 )
- 2020年04 月( 15 )
- 2020年03 月( 15 )
- 2020年02 月( 14 )
- 2020年01 月( 17 )
- 2019年12 月( 15 )
- 2019年11 月( 15 )
- 2019年10 月( 16 )
- 2019年09 月( 13 )
- 2019年08 月( 14 )
- 2019年07 月( 10 )
- 2019年06 月( 14 )
- 2019年05 月( 14 )
- 2019年04 月( 17 )
- 2019年03 月( 17 )
- 2019年02 月( 14 )
- 2019年01 月( 9 )
- 2018年12 月( 17 )
- 2018年11 月( 11 )
- 2018年10 月( 15 )
- 2018年09 月( 17 )
- 2018年08 月( 13 )
- 2018年07 月( 12 )
- 2018年06 月( 12 )
- 2018年05 月( 16 )
- 2018年04 月( 20 )
- 2018年03 月( 17 )
- 2018年02 月( 14 )
- 2018年01 月( 14 )
- 2017年12 月( 18 )
- 2017年11 月( 14 )
- 2017年10 月( 14 )
- 2017年09 月( 16 )
- 2017年08 月( 15 )
- 2017年07 月( 15 )
- 2017年06 月( 19 )
- 2017年05 月( 14 )
- 2017年04 月( 14 )
- 2017年03 月( 17 )
- 2017年02 月( 13 )
- 2017年01 月( 17 )
- 2016年12 月( 13 )
- 2016年11 月( 15 )
- 2016年10 月( 12 )
- 2016年09 月( 14 )
- 2016年08 月( 10 )
- 2016年07 月( 13 )
- 2016年06 月( 16 )
- 2016年05 月( 14 )
- 2016年04 月( 19 )
- 2016年03 月( 17 )
- 2016年02 月( 27 )
- 2016年01 月( 43 )
- 2015年12 月( 16 )
- 2015年11 月( 22 )
- 2015年10 月( 19 )
- 2015年09 月( 19 )
- 2015年08 月( 19 )
- 2015年07 月( 22 )
- 2015年06 月( 19 )
- 2015年05 月( 21 )
- 2015年04 月( 19 )
- 2015年03 月( 18 )
- 2015年02 月( 21 )
- 2015年01 月( 16 )
- 2014年12 月( 20 )
- 2014年11 月( 25 )
- 2014年10 月( 30 )
- 2014年09 月( 21 )
- 2014年08 月( 20 )
- 2014年07 月( 6 )
M8, M9 & R-D1 for Someting I love ...323...
田草月日記(7)...
2024年05月23日 
テーマ:テーマ無し
お酒を飲むと顔が赤くなる人は,ならない人に比べて約5倍新型コロナウイルス感染症にかかりにくいという興味深い記事があった.
佐賀大学医学部の松本明子准教授と同大研究員の農水省高島賢氏ほかの方たちのグループが研究したもので,既に日本衛生学会会誌Environmental Health and Preventive Medicine (EHPM), 2024, Vol.29:14に"Asian flush is a potential protective factor against COVID-19: a web-based retrospective survey in Japan"(DOI: https://doi.org/10.1265/ehpm.23-00361として発表されている.
コップ1杯のビールで顔が真っ赤になったり,頭痛,動悸が激しくなる体質をアジアンフラッシュという.これは、酒に含まれるエタノールを分解したときにできる代謝物のアセトアルデヒドによるもので,これを解毒する酵素の一つで,ヒトの染色体第12番遺伝子に存在する遺伝子,2型アルデヒド脱水素酵素(ALDH2)の遺伝子多型のひとつがrs671変異型となっているために起きる現象で,東アジア人に特有の体質であるためアジアンフラッシュと呼ばれる.日本人の約半数がこれに該当する.
欧米人にはこの変異型を持つ人は少ない.だから映画で見るように,平気でウイスキーやバーボンなどをおつまみもなしでクィーっと一杯やることができるわけである.
准教授は,皮膚が赤くなるマウスとそうでないマウスに結核菌を投与した研究で,赤くなるタイプのマウスの方が結核菌の増え方が少なかったという研究をすでに発表していて,アジアンフラッシュ体質の人はアルデヒド類を解毒しにくいため,普段から体内のホルムアルデヒドの濃度が高めで,そのことがウイルスからの防御になっているのではないかという仮説を以前より持っていた.また,高島氏によると,植物が細菌やウイルスの病気をアルデヒド類を使って防御している例もあることなどから准教授と共にこの研究を行っていた.
この研究は,昨年8月にインターネット上で807人について調査し,飲酒で顔が赤くなると答えた人は445人,ならないと答えた人は362人だった.このうち,2回目のワクチン接種が進んでいた2021年8月末までに新型コロナに感染した人は,アジアンフラッシュ体質でない人を1とすると,アジアンフラッシュ体質の人は0.21で,感染の確率は約5分の1だったという結果だったというもの.
全期間でみても,アジアンフラッシュ体質の人はそうでない人に比べて罹患率も入院率も低く,発症の時期も遅くなる傾向があったことがわかったという.あるいは,罹っても軽症だったということもあったようだ.
Des cerisiers en fleurs, des ombres et un p?re et son fils sur un petit pont...
Leica M10+Color-Skoper 21mm F4
松本准教授は,佐賀大のHPの「さがシーズ musubime」において次のように語っています(そこでは,ALDH2多型rs671の1型の研究についても解説されています):
「日本のCOVID-19罹患率および死亡率は、OECD加盟国38ヶ国の中で最下位層に位置します.今回の研究から,アジアンフラッシュ体質がCOVID-19の防御因子の一つであることが示唆され,日本における低いCOVID-19罹患率および死亡率を説明し得る因子を提示することができたと考えています.生物学的なメカニズムとして,ALDH2酵素の機能低下により体内に比較的高濃度に蓄積し得る内因性アルデヒドによる抗菌作用などを想定しています.
本研究は,東アジア特有の疾病構造の理解や医療の最適化に有用な情報を提供すると考えられます.アジアンフラッシュ体質は,COVID-19だけでなく,その他ウイルスや細菌,原虫による感染症,および免疫能に関連する疾患リスクにも影響する可能性が考えられます.今後はメカニズムの検証を進めると同時,新型インフルエンザ感染症パンデミック(鳥インフルエンザ感染症がヒト感染能を獲得した後に生じることが懸念されています)を見据えた研究活動を計画する予定です」.
今回の研究は疫学的な面からのもので,准教授も述べるようにその作用機序が明らかにされなくては証拠が足りない.興味深い切り口で他の感染症との絡みも追求できる可能性が大きいからこそ,更なる研究の進展を期待したい.
>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)
この記事はナビトモではコメントを受け付けておりません