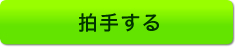メニュー
最新の記事
-

【New!】 『のっけから失礼します』 読書日記384 -

【New!】 『100万回死んだねこ』 <旧>読書日記1601 -

【New!】 『ランチ酒 おかわり日和』 読書日記383 -

『金の穽(オトシアナ)』 <旧>読書日記1600 -

『最果ての森 妖国の剣士6』 読書日記382
テーマ
カレンダー
月別
- 2024年06 月( 10 )
- 2024年05 月( 26 )
- 2024年04 月( 26 )
- 2024年03 月( 26 )
- 2024年02 月( 24 )
- 2024年01 月( 27 )
- 2023年12 月( 31 )
- 2023年11 月( 30 )
- 2023年10 月( 31 )
- 2023年09 月( 30 )
- 2023年08 月( 31 )
- 2023年07 月( 27 )
- 2023年06 月( 30 )
- 2023年05 月( 31 )
- 2023年04 月( 28 )
- 2023年03 月( 31 )
- 2023年02 月( 26 )
- 2023年01 月( 31 )
- 2022年12 月( 31 )
- 2022年11 月( 29 )
- 2022年10 月( 15 )
- 2022年09 月( 15 )
- 2022年08 月( 15 )
- 2022年07 月( 17 )
- 2022年06 月( 15 )
- 2022年05 月( 15 )
- 2022年04 月( 15 )
読書日記
『あぶない法哲学』 <旧>読書日記1358
2023年03月31日 
テーマ:<旧>読書日記
住吉雅美『あぶない法哲学』講談社現代新書
常識に楯突く思考のレッスン、という副題の本。「はじめに」によると、著者は法哲学を以下の様に説明する。
そもそも哲学とは、既成の知を徹底的に疑い、<存在すること>の根拠は何であるのかを探求し続ける思考だ。私たちが自明としている常識を問い直し、思い込みを問い質し、そして真理の探求へと向かう。
法哲学は、法律に炊いてその思考を向ける。つまり、人間社会のさまざまなルールの中で、なぜ法律だけが国家権力による強制力をもつことができるのか。そのような法律を成立させ存在させるものは何なのかを問う、古代ギリシアに起源を持ち、ヨーロッパで発展した歴史ある学問である、と。
さらに、著者は法哲学には2つの顔つまり天使の顔と悪魔の顔があると言い、本書はその悪魔の顔を持つ法哲学、つまり哲学的な視点で法律や常識を批判的に再検討するがテーマである、とする。
はじめに
第1章 社会が壊れるのは法律のせい? −法化の功罪
第2章 クローン人間の作成はNGか? −自然法論vs法実証主義
第3章 高額所得は才能と努力のおかげ? 正義をめぐる問い
第4章 憲法に逆らうワルになれ! −遵法義務
第5章 年頃の子に自由に避妊させよう −法と道徳
第6章 大勢の幸せのために、あなたが犠牲になってください −功利主義
第7章 人類がエゾシカのように駆逐される日 −権利そして人権
第8章 私の命、売れますか? −どこまでが「私の所有物」か
第9章 国家がなくても社会は回る −アナルコ・キャピタリズムという思想
第10章 不平等の根絶は永遠に終わらない −どこまで平等は実現できるのか/するべきか
第11章 私には「誰かに食べられる自由」がある? −人はどこまで自由になれるか
読書案内
おわりに
読んで見ると、法律寄りの議論は1章と2章であとは哲学寄りの議論であった。それこそ古代ギリシアのソクラテスやプラトン、アリストテレスの時代から続いている議論であると言っても良い。そして法律自体はもっと昔のハンムラビ法典(歴史的にはこれは最古の法典では無い)の頃からある。ただ、その頃に法哲学はあったかどうかであるが・・そういう意味ではどちらが先の学問かを問うても意味は無いだろうし、法と倫理・道徳(哲学の一分野)とのどちらが上位概念としてあるかも微妙な問題となる。
そして、「既成概念に対しての疑い」こそが哲学の本質であり、領域であると私は考えており、その疑いの範囲もまた哲学の方が広いと思っているのである。それ故に、本書での問いや考察の対象はほとんどが(私にとって)既知であり、その限りにおいては新鮮とは言えなかったが、意外と法哲学だけでも範囲は広いと思ったし、著者の概念整理が秀逸なこともあってロールズの「正義論」など改めて理解が深まった部分もあった。
(2020年8月12日読了)
コメントをするにはログインが必要です